映画や本や雑誌で、いまなぜか話題高まる硫黄島に行ってきた。より正確には、昨年12月13日、思いがけず、いま自衛隊機でしか行けない硫黄島の地を踏む幸運に恵まれた。 私が共同通信勤務中、ニューヨーク、ワシントン、バンコク、ワシントンーと通算10年を越す特派員生活を送ったおかげで、会員となっている財団法人日本外国特派員協会、通称外人記者クラブが防衛庁(当時)の協力を得て企画した15人限定の「硫黄島スタディー・ツアー」のくじに約三倍の希望者の中から当たったからである。外人記者クラブの狙いが、硫黄島戦をアメリカ、日本の両サイドから描いたクリント・イーストウッド監督の二部作、「父親たちの星条旗」と「硫黄島からの手紙」の公開にあわせた、「読み物」づくりの旅であることは明らかだった。
○ 緊張して準備
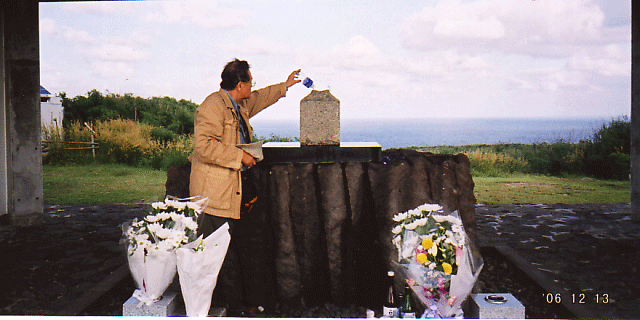
しかし、私は大いに緊張した。拙著「銃を持つ民主主義―アメリカという国のなりたち―」などで、繰り返し述べているように、私は62年前に終わったあの戦争でアメリカと出会った。昭和8年生まれ。小学6年生(当時は国民学校と呼ばれた)で、日本の敗戦を経験した。8月15日は、墳墓の地である福井県の大野市で迎えた。その一ヶ月前には、福井市で、B29、 127機の「夜間無差別焼夷弾爆撃」を受けた。しかし、欠陥親爆弾のおかげで田んぼの泥水を防空頭巾に浴びただけで、九死に一生を得ていた。市内の尼寺、菩提寺に下宿しながら有終小学校に通い、週末は12キロの山道を歩いて母親たちが逃げ延びていた曹洞宗の名刹、宝慶寺を訪れる毎日だった。旧陸軍の職業軍人の子供だったこともあって、漠然とながら、死を前提とした「本土決戦」の日々を意識し始めていた。その私にとって、追い詰められた日本の自らの固有の領土内での初めての激しい地上戦闘の舞台となった硫黄島の土を踏むことは、特別なことだった。 すぐイーストウッド監督の二部作を二本とも見て、硫黄島守備隊司令官だった栗林忠道中将がアメリカ駐在時代に自宅に送り続けた絵手紙をまとめた「玉砕総指揮官」の絵手紙(小学館文庫)など数多い硫黄島関係の著作のいくつかに目を通し、防衛研究所の専門家の話も聞いた。そして、1995年に硫黄島を訪れたことがある友人からの、水を求めながら死んでいった日本兵たちの供養に水を持っていくようにとのアドバイスを受けて、外国原産ではない日本の名水のボトルをさげて、埼玉県入間基地から航空自衛隊の輸送機、C-1に乗り込んだ。
○ 火炎放射器のタンクがごろり
約二時間半の飛行で、全周24キロ、総面積約22平方キロ、文字どうりの絶海の孤島、硫黄島に着く。ちなみにこの島の番地は東京都小笠原村硫黄島、つまり立派な東京都内なのである。しかし、そこには私の中から62年間消えていたあの戦争が目の前に現れた。痛々しい傷跡がそのまま残っていた。 昼食の後すぐ連れて行かれた海上自衛隊硫黄島基地隊の資料室に入ると、床の上に赤さびたアメリカ軍使用の火炎放射器用の燃焼剤タンクがごろりと置かれていた。10日ほど前に見つかったばかりのものだという。その隣には、半壊した旧陸軍の92式重機関銃。
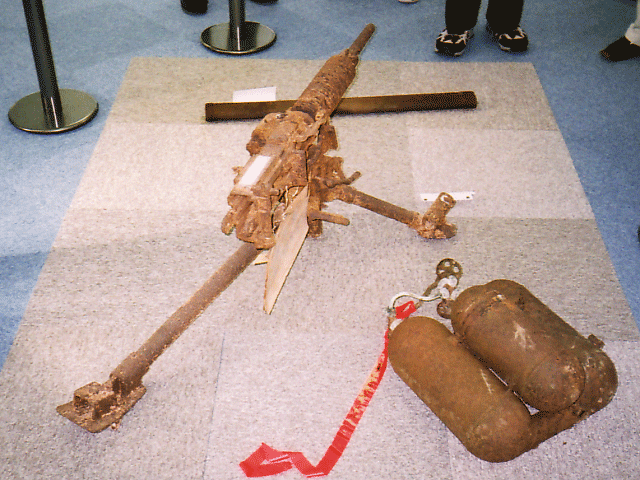
小型バスで島内を案内されると、地上で破壊された日本軍機の胴体を生かした半地下壕陣地跡。旧海軍の巡洋艦の副砲だったという口径15インチの水平砲。アメリカ軍が占領後、日本兵の死臭を消すために、空からまいた種が根付き、今ほぼ全島をおおうねむの木の背の低い潅木林の中に入ると、こうした兵器の残骸はまだまだ出てくるという。 期待していた日本軍側の抵抗の拠点となった地下、半地下の洞窟陣地壕跡の見学は、安全確保という点で厚生労働省の許可が下りていないということで、制限されており、栗林司令部跡や西戦車連隊司令部跡などには連れて行ってもらえなかった。安全基準をパスしている数少ない壕のひとつということで、今回唯一中に入れてもらえた旧海軍の病院壕には、当時の医療器具の残骸などがそのままさび朽ちている。

しかし、心が痛んだのは、温度の高さだった。入り口付近で40度、行き止まりの最深部では、60度が記録された。わずかに一ヶ所、はるかに地上に通じ、青空がのぞく縦穴から湿った空気が流れて来ていた。一瞬、この暑さの中で、こうした洞窟陣地にひそみ、雨水をためただけのわずか水を分け合って戦い続けた日本兵士の過酷な状態に触れた思いだった。
○ 過酷な持久戦
結局、滞在時間わずか五時間足らずという今度の訪問で、一番肌で感じたのは、この硫黄島戦の過酷さ、残酷さだった。一つは、戦闘そのもののすさまじさだった。アメリカ軍は上陸に先立ち、海と空から猛烈な砲爆撃を行った。防衛研究所の資料では、1945年2月19日の上陸に先立ち、三日前から戦艦7隻、重巡4隻、駆逐艦15隻などによる艦砲射撃を開始、以後3月25日までの計算で、打ち込んだ砲弾総数は14,250トンという。おかげで島のシンボルである標高169メートルの摺鉢山の南側は変形したという。前年の12月から組織的に始まった空からの爆撃は、投下爆弾約8,360トン以上(ロケット弾12,148発、ナパーム弾456個も含む)という激しさで、全島が少なくとも表面は瓦礫の山になったような状態にしたうえでの、海兵隊三個師団約7万人の上陸だった。

これを迎え撃った陸海軍あわせて約2万人の日本軍の栗林司令官は、すでにサイパン島などの陥落で机上の空論となっていた大本営の水際での抵抗で上陸を許すな、との作戦指導を自ら具申して修正し、総延長18キロにわたる地下、半地下の洞窟陣地と二段構えの複郭陣地を構築した。「地下要塞」化による持久戦体制に持ち込もうという作戦だった。場所によっては硫黄が噴出する灼熱の大地の中に、洞窟陣地を掘る作業は、10分で交代しなければならない難業だったという。 このため、最初は5日間での占領をもくろんでいたアメリカ軍は苦戦する。上陸後約1時間後に突如として始まった日本軍の反撃に虚をつかれて大混乱、この数時間だけで約3,000人が死傷する。従って、死傷者総数では、アメリカ軍28,686人(うち戦死者6,821人)に対し、 日本軍は20,933人(うち戦死者19,900人)とアメリカ側の犠牲の方が多い、ドイツ戦線を含めて第二次世界大戦全体で他に例のないケースとなった。完全制圧まで約一ヶ月半近くかかった。 私たちが、いきなりその残骸を目にした火炎放射器は、アメリカ側がこの苦戦を乗り切る最後の手段として多用された。この燃焼剤タンクを背負ったアメリカ兵が日本兵のひそむ洞窟陣地に炎を打ち込み、手榴弾を投げ込んで制圧し、最後はブルドーザーで壕全体を埋め尽くす「土木工事」のような作戦だった。
○ 知米派の指揮
もう一つ残酷だと思う話がある。指揮を執った栗林司令官が、当時の陸軍では数少ない「アメリカを知る」エリート将校だったことだ。騎兵将校としてエリートコースである陸軍大学校を二番で卒業した栗林司令官は、1928年からに2年間、アメリカ駐在の辞令を得て、各国軍事研修の一環として、首都ワシントンを始め、ハーバード大学での聴講生生活やカンザス、テキサスなどの騎兵部隊を訪問、アメリカ陸軍との交流に励んだ。特に栗林司令官は車(シボレー)を買い、自ら運転してアメリカ各地を旅した。この間、東京の留守宅にいる幼い長男宛にこまめに書き送った絵手紙をまとめた「玉砕指揮官の絵手紙」(小学館文庫)によると、「アメリカはどこに行っても広いなあ。これを考えると、日本はほんとに惨めなものだ」、「こんな婆さんの(下宿先のメイドのこと)自動車でも、日本の田舎を走っている乗合自動車より、よっぽどいいや。ほんとに日本もどうかしないといけないなー」といった、アメリカの国力を日本のそれと比較してクールに捉える観察を残している。 こうしたアメリカ経験が、最後まで、バンザイ攻撃など死に急ぐ形だけの「玉砕」を部下に許さなかったクールな指揮を生んだのだろうか。栗林司令官は、1944年6月の硫黄島赴任直後から妻や子供たちへの手紙ではっきり、生還不可能、つまり自らの死を前提としたこまごまとした指示を家族に書き送り、子供の手紙の誤記まで几帳面に直している。アメリカの国力、その物量のすさまじさを知る指揮官が、敗北を覚悟のうえであみ出した地下壕陣地による持久戦の悲劇に、私は二重の残酷さをみる。死傷者の数だけを数えて、「善戦」などという言葉はとても使えない。 私は、アメリカの黒船によって近代化の第一歩を踏み出しながら、結局、最後にはあの戦争という最大の“すれ違い“を演じてしまった、明治以降の日本とアメリカとの不幸な関係が凝縮され、今も硫黄ガスが噴き出すこの島に投げだされているように感じた。もう一人、硫黄島ではアメリカを知るエリート将校が戦死している。1932年ロサンゼルス五輪の馬術大障害金メダリスト、西竹一大佐である。 アメリカ兵が星条旗を打ち立てたので有名になった摺鉢山山頂の慰霊広場では、偶然、毎年恒例の行事だという硫黄島研修に参加している戦闘服姿の防衛大学校学生の一団と出会った。アメリカ軍が上陸した南海岸を眼下にしながら、熱心に教官の話に耳を傾ける女子学生も混じる将来のエリート将校の姿をみながら、彼らの世代での“すれ違い”は許してはならない、と思った。
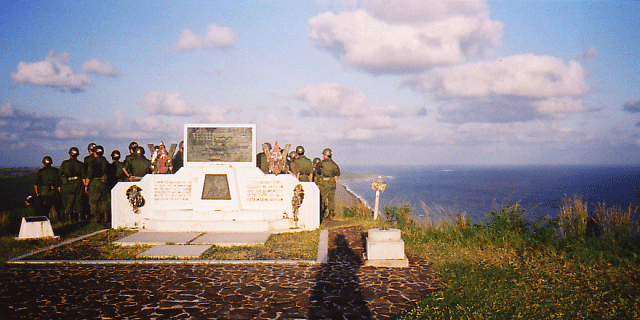
○ 遺骨回収をどうする?
そして美しい夕陽を浴びる島影を後にしながら、最後に強く心にひっかかったことがあった。硫黄島で戦死した日本側の死者、19,900人のうち13,600柱はまだ未回収であるという事実である。厚生労働省の報告では、1951年に遺骨回収が始まり、現在も年4回、1回に二週間の日程で実施されている作業は陣地を埋め尽くした「土木工事」との戦いで遅々としてすすまないのだという。 身近な「東京都内」での、あの戦争へのケジメの欠落に触れた思いで、「どうすればいいのだろう」と深く考え込みながら帰ってきた。このことは慎重に調べたうえで、近く提案をまとめたい。 最後に、イーストウッド監督の硫黄島二部作、「父親たちの星条旗」と「硫黄島からの手紙」に対する感想を述べておきたい。いずれも戦争のむなしさを鋭くついた立派な作品だと思う。しかし、私には、栗林司令官がありえない参謀肩章などをつけていたりする時代考証に難がある第二部より、「摺鉢山の星条旗」の英雄に仕立てられたインディアン兵士の悲劇にまで踏み込み、当時のアメリカ社会の自己矛盾を描いた第一部のほうが作品としての出来はよいように思えた。私が、拙著の第六章「差別」と「排除」(197ページ)で、このインディアン兵士、アエラ・ヘイズ上等兵の悲劇に触れていたからであったかもしれない。とにかく、クリント・イーストウッド監督に脱帽、である。
完(2007年1月21日)
